介護医療における今後のICTの活用方法を考える

「利用者ニーズの変化に応えるために医療・法律の面からできること」の第二弾として、今回は「介護医療における今後のITCの活用方法」について対談を行いました。
今回のメンバーは介護付有料老人ホーム「みなみいせ」の施設長の濱口さん、ドクターメイト代表であり医師の青柳さんです。
介護をめぐる様々な問題の解決にICTがどう活用できるのか、施設と医療の立場からお話していただきました。
【対談参加者プロフィール】
[jin_icon_account color=”#e9546b” size=”19px”]濱口 新太郎さん
三重県の有限会社ウェルフェア三重が運営する、介護付有料老人ホーム「みなみいせ」の施設長。
[jin_icon_account color=”#e9546b” size=”19px”]青柳 直樹さん(医師)
ドクターメイト株式会社代表取締役、医師。
介護事業所向けにオンライン医療相談や夜間オンコール代行などの医療サービスを提供する。
苦情やトラブルのリスクを回避するためのICT活用
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]施設内でのカンファレンス時、医師の参加が難しい点に課題を感じています。
ドクターはお忙しいのでなかなか都合が合わず、看取りについても、往診で来ていただいたときなどにご家族と会っていただいて、ケアプランに落とし込んでいるのが現状です。
苦情やトラブルのリスクマネジメントとして、やはりカンファレンスで医師の意見を聞くことが必要ではないかと最近再認識しています。
そのためにICTを活用し医師との連携を取りたいと思っていますが、医療面での意見をお聞かせください。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]ICTの活用でいうと、私は医療者も診断、治療以外ではオンラインをしっかり活用していくべきだと思っています。
地域の偏在もありますし、全てをリアルで対応しようというのはお互いに難しいですよね。
例えばご家族への説明や職員との相談はオンラインでも良いと思います。
国としても、オンラインでできる部分はオンライン化していきましょうという流れになっているので、現場もその流れに乗ってオンライン化を進めて良いのではないでしょうか。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]実際にこの3年間、いろんなものについてオンラインで行う可能性を広げてきましたよね。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]例えばご家族への説明はオンラインで良いという前例を作ることですよね。
それをベースに今後のやり方を考えていくことで、現場もご家族も医療者もお互いに負担が減ると思います。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]事故訴訟などのトラブル回避についてはいかがでしょうか?[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そこに関しては原因が二つあると思っています。
一つ目は事故が起きた時にご家族の方がそもそも医師の顔を知らない、普段からの信頼関係が構築できていないことです。
そこはオンラインでコミュニケーションを増やすことで解消していけると思います。
二つ目は起きた時にもっと早く気がつかなかったのか、その間の経過はどうだったのかという点です。
経過が分からず記録に残ってない場合、医師もアドバイスのしようがありません。
なのでICTを活用して写真などのデータを残したり、我々ドクターメイトのような外部の医師にアドバイスを求めて記録し、途中経過も含めて分かるようにしておくことでトラブルを減らせると思います。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]確かにそうですね。私たちもご家族との関係性は構築しておかないとトラブルの元になると感じています。
そのためにも入居時に ACP(Advance Care Planning)をしっかり取るというのが最近の流れですね。[/chat]
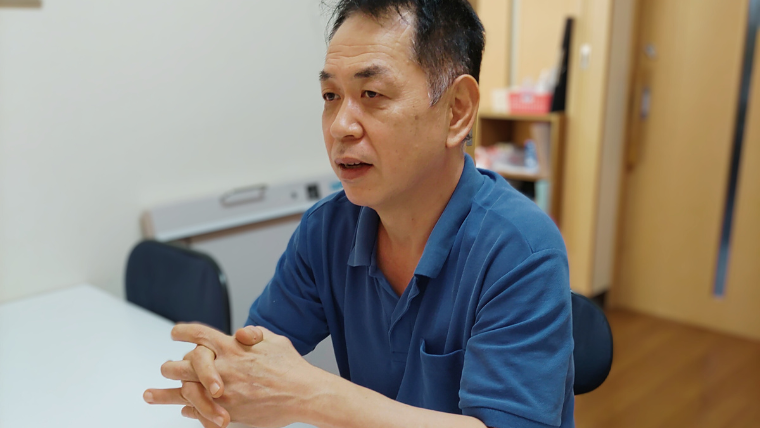
ポリファーマシーに関するICT活用
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]最近、もう一つ重要な課題だと感じているのが「ポリファーマシー」です。
薬剤師が医師と連携をとりながら薬の飲み合わせや、副反応に対するアプローチを積極的に行う流れになっていますが、この問題に関してはいかがですか?[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]ポリファーマシーで問題が起きるとしたら、大きく分けて二つ要因があります。
一つはその人が飲んでいる薬が分からない、いわゆるバラバラの医療機関から様々な薬を処方されているという点です。
二つ目はその薬をやめるポイントが明確でないということです。他の嘱託医がその薬をやめていいのか判断がしにくい状況が生まれてしまいます。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]私もそういう局面に何回も立ち会ったことがあります。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]一つ目の課題の解決策としては、飲んでいる薬を電子処方箋にし、その情報をデータベース化しようと国でも整備を進めています。
今後3〜5年で一元管理ができるようになるのではないでしょうか。
二つ目については、処方される時に「いつを目処に状態を評価したらよいか」をセットで現場と医師とでコミュニケーションを取ることです。
ここについて解決できるICTができれば便利になりますよね。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]それは助かりますね!救急で運ばれた場合に、なぜその薬を飲んでいるかと聞かれても現場がそこまで把握できていなくて困ることがあります。
ご家族からも、なんで管理できていなんだと言われて辛い思いをしたことも。これからはICTを活用し、医療との連携をより密にしていくことで解決したいですね。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]処方箋に変えないで欲しい薬、現場の判断でOKの薬という印があると良いですよね。[/chat]
医師と現場をオンラインで繋げることで往診の形を見直す
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]薬についてもですが、このコロナ禍で往診の形もだいぶ変わってきたなと思っています。
ポータブルレントゲンの登場でこの辺りの技術開発が進むとよいなと思っています。
スマホで撮って情報を医療機関に送れるなどのサービスがあれば、現場の負担がだいぶ減ると思います。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そうですよね、これからさらに進んで行く分野だと思います。
現在、聴診器など遠隔でできるデバイスが出てきていますよね。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そういう時代になって欲しいですね。職員が医師の助手的な作業をして、情報を集めて送るというのが理想的だと思っています。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]おっしゃる通りですね。
在宅の場合にその作業をやるのは難しいですが、施設であれば利用者さんの普段の様子を見ていますし、職員への教育なども含め導入しやすいと思います。
私は施設の職員と連携をする前提の医療をもっと推し進めるべきだと、国へも提言しています。
医療DXと言われていますが、医療介護DXを推し進めていかないと根本的なこの国の問題は解決できません。
国としてもその流れはできてきているので、今後は現場に負担のかからないICTを活用した医療との関わり方が増えてくると思います。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]現場と医師とお互いにメリットが大きいですよね。
施設に往診している医師の苦労をお聞きする機会があって本当に大変なんだと思いました。
人手がないこともあり、なり手がいなくなるのではと危惧しています。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そうですね。ICTを使い医師にも負担なく関われる形を作ることは、とても意義深いと感じています。[/chat]
今後増えていく看取りに関するICT活用
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]ICTの活用に関していうと、看取りに関しても医療との連携が取れないかと思っています。
急死や深夜の場合、医師が中々施設に来られないことが多くあり、体制として限界がやってくると思います。
この問題をICTで解決できないでしょうか。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]今後看取りは必然的に増えていくので、その中で医療側としてもリアルに駆けつけることができなくなっているのが現状ですよね。
実はICTを活用した看取りは実際にありまして、新しい仕組みを作っていこうという動きが今まさに始まってきたところです。
その仕組みは研修を受けた看護師が駆けつけ、全身隈なく写真に撮りオンラインで医師に死亡診断書を書いていいかの依頼をする。
そしてその医師は14日以内にリアルにその方の診断をしていれば書けるというものです。
ただそれができる看護師は、大学病院で相当な時間の研修を受ける必要があるのでハードルがかなり高いんです。
そのため実用的かと言われるとまだまだです。今後、実例が多くなっていけば、施設の看護師と協力しながら看取りをしていくことが進んでいくと思っています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そういう仕組みがあるんですね!国は病院だけではなく、介護施設でも積極的に看取りを行ってくださいと言っている割には、中々整備が進まないと感じていました。
看取りばかりになっている施設もあり、訪問診療されている医師も大変だと思います。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]国は2030年には在宅、施設を含む看取りを38%にするという数字を掲げています。
間に合いますか?という気持ちもありますが、方向性は一致しているので声をあげていきたいですね。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]いいお話が聞けてよかったです。看取りは本当に大変なので、手当もですが仕組み自体をスムーズにする必要がありますね。[/chat]
二極化するIC化は入り口の体験が重要に
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]ICTの活用について現場、医師ともに考えが二極化していると感じています。
青柳さんは今後、活用すべきになると思いますか?[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]私は活用すべきになっていくと思います。
今ちょうど二極化しているタイミングですよね。
ICTという言葉を聞いたときの第一印象で、便利になりそうだと感じる人と、面倒が増えそうだと感じる人がいると思います。
面倒が増えそうだなと感じる人へは、具体的にあなたの業務のここが楽になりますよ、という説明をしないと納得しないのではないかと思っています。
なのでICTを活用できている人たちの実例を作り、発信していくことが必要です。
そうすることで世の中的にICT化をしていこうという方向にいくと思います。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]私はこれから訪問診療などもありますし、物理的にICT化を進めざるを得ない状況になっていくと思っています。
コロナ禍で強制的にICT化が進みましたが、コロナ禍が明けても研修や認定審査会などはオンラインを続けています。あとはどう簡単になるかだと思います。
ICT化への抵抗感を払拭するには入り口を簡単にしなければいけません。
ボタンひとつでいいという簡単な切り口が一番だと強く感じています。
難しい場合は丁寧に説明するのにも人員をさかなくてはいけません。そうすると多くの施設を抱えている法人だと不可能です。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]使うか使わないかの判断は入り口の体験によりますよね。
なのでドクターメイトではプロダクト開発、マーケティング、セールス含めてUI、UXにこだわって作っています。
社内で私はまずは顧客価値という目線が大切だという話をしています。
お客様がこうだったら使いやすいのではないか、という目線で全てを設計するということです。
ただお客様の声を聞いて形にするだけでは60%の出来です。お客様のお話を聞いて、その上で我々がもっと良いものの仮説を立てて提案するということが必要です。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]並々ならぬ苦労をされていると思います。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]お客様が本当に欲しいものというのは言葉にできないと思います。もしかしたらこういうことに困っているのではないか、だったら本当はこういう機能が欲しいんじゃないかという思考をすることですね。ここまでできるようになるのがベンダーの責務だと思っています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]素晴らしいと思います。
現場もこの問題を解決できる方法はないかと提案するなど、一緒に参画する意識が大切ですね。
本当に完成しているプロダクトはないと思うので、私たちの意見も反映していただけるかはすごく重要視しています。
「作りましたよ、はいどうぞ」で終わると困りますね。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]おっしゃる通りです。これはベンダー全員が意識しておかないといけません。
「競合がこの機能を付けたからうちも付けよう」では、全然現場のことを考えていません。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]現場のことを考えてくれるベンダーが増えてきているのでありがたいと思っています。[/chat]

ドクターメイトの今後の展開は?
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]現在はオンラインの仕組みを使って医療相談、オンコール事業を展開していますが、今後のドクターメイトの展開はどうでしょうか?[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]ICTを活用した医療アプローチをより強化していこうと思っています。
例えば施設からの受診が難しい診療科に関しては、オンライン診療で全て受けられるようにするなどです。
医療教育も外部にいくのではなく、システム上で教育を行うなどもいいと思います。
外と中から介護施設のケアの質を高めていくお手伝いをしていきたいですね。
そこからデータを取って国への提言もしたいと考えています。
職員の負担軽減もそうですが、利用者もそれを支える医療も、お互いに負担少なく持続可能なwin-win-winな介護の形を目指したいと思っています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]その通りですね。先日、ドクターメイトさんが全国に拠点を作るという話を伺いましたがどのようなものですか?[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]訪問看護ステーションのことですね。
現場に常に医師が行くことが難しいため、看護師が駆けつけオンラインで医師と相談しながら、医療的な対応をするということを考えています。
私は実行に移したいと思っていますが、今はタイミングをみています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]規制を緩和して施設でやれることの範囲を広げていくか、そのような拠点を増やして全国的に展開していただくかどちらかですよね。
夢のような話ですが、例えば職員がグローブなどの器具を使って、医師の触診の手助けになるようなシステムなど、遠隔で医師の診療の「手助け」ができるようになるといいなと思います。
越権しない範囲でICT化が進んでいくといいと思いますので、ドクターメイトさんの事業にはすごく期待をしています。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]そのために固定観念を変えるアクションをしていくことが、現場からベンダーに期待されていることかなと思っています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]私は20年30年先のことを考えているかを職員にはよく問いかけています。
今が良ければいいのではなく、その先のことを考えないといけません。
これから続けていける仕組みを作っていかないといけないと強く感じています。[/chat]
[chat face=”interview-doctormate-medical-law-square-aoyagi.png” name=”青柳さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]私もどんどん発信をしていこうと思っています。[/chat]
[chat face=”hamaguchi-scaled-e1630397154401.jpg” name=”濱口さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=”maru”]よろしくお願いします!介護に関わる全ての人が良くなる仕組みを、一緒に作っていきたいですね。今日は勉強になる話をありがとうございました。[/chat]
DXは導入するだけではただのIT化で終わってしまいます。
医療介護DXをするには、きちんと活用し、利用者や職員、医療者それぞれにメリットをもたらさなければ意味がありません。
そして国も現場の業務をオンラインでできるように、ICT化に向けて大きく動き出しています。
だからこそ現場もしっかりとICTについて理解し、追従していくことが大切なのではないでしょうか。






